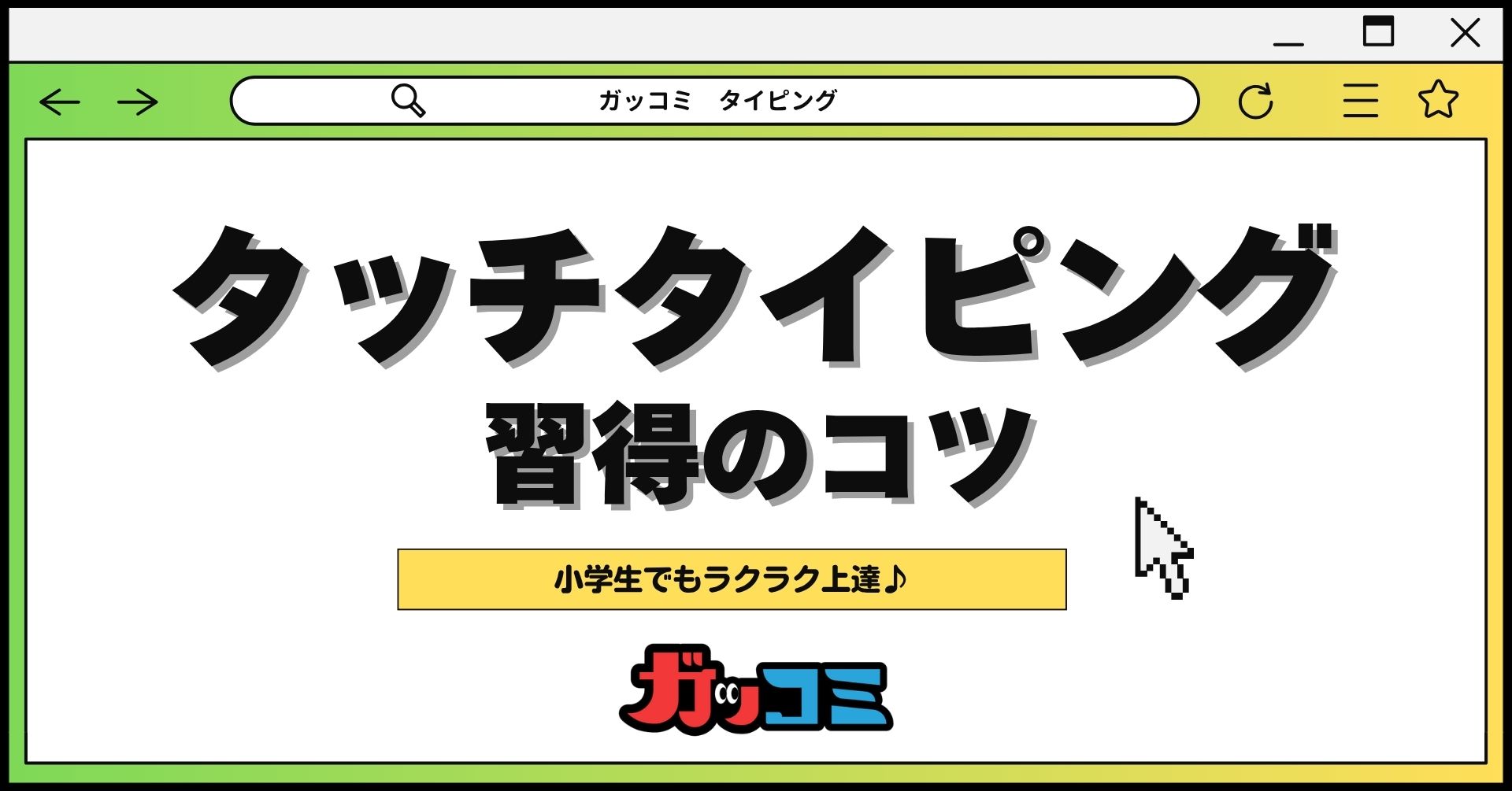【中級者向け】タッチタイピングのコツと毎日の習慣化テクニック|タイピング練習を続けて上達する方法
2025年08月04日10時00分
タイピングを上手に、そして速くできるようになるためには、ただなんとなく練習するだけでは足りません。毎日、正しいやり方で練習を続けること、そしてキーボードを見ないで打てる「タッチタイピング」を身につけることが大事です。
このページでは、タイピングが上手になるための考え方や練習のやり方、そしてタッチタイピングを覚えるためのステップを、わかりやすくまとめています。自分のペースで、少しずつうまくなっていきましょう◎
👉 「タイピングをこれから始めたい!」という人は、こちらの記事も見てみてね!
【初心者向け】タイピングを速くする方法は?小学生でも簡単に習得できる練習のコツを伝授!
タイピングは“続けること”が一番の近道

タイピングが上手になるためには、「毎日続けること」が一番の近道です。一度にたくさんやるよりも、少しの時間でも毎日こつこつ続けた方が、手がキーボードの動きになれていきます。
なぜなら、「どの指でどのキーを押すか」が、少しずつ体にしみこんでいくからです。
少しずつできることが増えてくると、タイピングがもっと楽しくなってきます。時間をはかったり、自分の記録をのこしたりするのもおすすめです。
タイピングの上達に、特別な力はいりません。
「今日もちょっとやってみよう」という気持ちの積み重ねが、未来の自分の力になります。
タッチタイピングのきほんと練習のしかた

タイピングが速くて、まちがいが少ない人の多くは、「タッチタイピング」ができるようになっています。
タッチタイピングとは、キーボードを見ないで文字を打つ方法のことです。これができるようになると、手元を見なくてもスラスラと文字が打てるようになり、作業のスピードも大きく上がります。
このわざは、一日でできるようになるものではありません。でも、正しい指の使い方をおぼえて、練習を続ければ、だれでもできるようになります。
これから、タッチタイピングのきほんと、どうやって練習すればよいかをしょうかいします。まずは「見ないで打てるようになる」ことを目標にして、少しずつ前に進んでいきましょう!
タッチタイピングってなに? 見ないで打てるようになる仕組み
タッチタイピングは、さいしょはちょっとむずかしく感じるかもしれません。でも、やり方がわかれば、だれでもできるようになります。
うまくなるためのポイントは、「ホームポジション」とよばれる、指の置き方です。キーボードのFとJのキーには、小さなでっぱりがあります。そこに人差し指を置くと、ほかの指も自然と正しい場所にそろうようになっています。
この指の場所をおぼえておけば、手元を見なくても、キーの位置がだんだんわかるようになってきます。
タッチタイピングの練習をするときは、いきなり全部のキーを打とうとしなくて大丈夫。よく使うキーから、少しずつおぼえていくのがコツです。そして、画面だけを見ながらゆっくり打つことで、少しずつ感覚で打てるようになってきます。
まちがえても気にしなくて大丈夫。
「見ないで打つ」をくり返すことで、自然にできるようになっていきますよ。
タッチタイピングを習得するための練習ステップ
タッチタイピングを覚えるための基本ステップを4つにわけて紹介します。
ステップ1:ホームポジションを完ぺきにする
まずは、キーボードの「F」と「J」のキーに人さし指を置いてみましょう。そこから順番に、左右の指を正しいキーに置きます。この形を「ホームポジション」といいます。毎回ここに戻るクセをつけることで、手の動きが安定します。
ステップ2:中央のキーだけで練習する
次に、「A・S・D・F・J・K・L」など、ホームポジションにあるキーだけで打てる文字を練習します。たとえば「さしすせそ」など、打てる言葉をくり返し練習して、指の動きになれましょう。
ステップ3:少しずつほかのキーに広げていく
中央のキーになれてきたら、次は上の段や下の段のキーにも広げていきます。たとえば「E」や「N」など。知らない場所に手を伸ばすときも、打ち終わったらホームポジションに戻るようにします。
ステップ4:見ないで画面を見ながらタイピング
最後に、「手元を見ずに画面だけを見る」練習をしていきます。最初はゆっくりで大丈夫。打ちまちがえても気にせず、くり返し練習しましょう。だんだんと手がキーの場所をおぼえていきます。
タイピングを毎日続けるコツ

タイピングは毎日少しずつでもやることで、うまくなっていくスキルです。
たとえば、宿題のあとに5分だけ練習する、朝学校に行く前に10分だけやる、というふうに、自分の生活の中にタイピングの時間を組みこむことがポイントです。
自分にぴったりの時間に練習すれば、続けやすくなります。そして、習慣にすることで、「今日はどうしようかな」と迷わず、スムーズにタイピングに取りかかれるようになります。決まった時間にやるだけでなく、終わったら自分に「できたね!」とほめるのも大事です。タイピングは、特別なことではなくて、「いつものこと」にしていくのが上達の近道です。
タイピング練習は毎日5分でもOK!
タイピイングは「毎日長い時間やらないと上手にならない」と思っていませんか?
実は、そんなにたくさんやらなくても大丈夫です。タイピングは、短い時間でも毎日続ければ、必ず上手になります。ポイントはとにかく“毎日”やることです。 たとえば、1日5分だけでもOKです◎
時間をはっきり決めておくと、ゲームやテレビよりも先にタイピングをすませることができて、気持ちもすっきりします。タイマーを使って「5分だけやる」と決めるのもおすすめです。
また、練習した内容や打った文字の数、どれくらい速く打てたかを記録していくと、「こんなにできるようになった!」と自分でもびっくりするくらい、成果が見えてきますよ。
「ポコ★タイピング」で楽しくタッチタイピングを身につけよう
タイピングをもっと楽しく、わかりやすく学びたいときは、タイピングのゲームを使うのもおすすめです。 「ポコ★タイピング」は、ストーリーゲームを攻略することでタイピングが上達できるので、毎日文字ばかりを打つだけでは飽きてしまうという方にもおすすめです。また、タイピングのレベルアップが目に見えてわかるので、「もっとやりたい!」という気持ちにつながります。
『小学生のためのタイピングスタディブック』

「ポコ★タイピング」の攻略本にもなっている『タイピングスタディブック』では、文字の打ち方だけでなく、ホームポジションの指の使い方などタイピングにまつわる様々な知識が、やさしく説明されています。絵や図が多くて、読むだけでもイメージがつかみやすくなっています。
この本のいいところは、「どこから始めればいいかわからない」という方でも、自分のレベルに合わせて始められるところです。最初はひらがな、次にカタカナ、そして文章へと、段階的に進められるので、自然と力がついていきます。
さらに、練習ページには「書いて覚える」「声に出す」など、体を使った学びも取り入れられていて、覚える力がぐんと高まります。家庭でも学校でも使いやすい内容なので、タイピングを本気で学びたいなら、ぜひ使ってみてください。
まとめ:タッチタイピングは、毎日の積み重ねで誰でもできる!
タイピングがうまくなるためには、「続けること」と「タッチタイピングを身につけること」がとても大切です。どちらも一日でできるようにはなりませんが、毎日少しずつ練習を続ければ、少しずつ上手になります。タッチタイピングは、最初はむずかしく感じるかもしれません。
でも、ホームポジションをしっかり覚えて、画面を見ながら打つ練習をくり返せば、必ずできるようになります◎
コツコツ練習を重ねれば、かっこよくスラスラ文字が打てるタイピングマスターへの道が見えてくるはず! 毎日5分でもいいので、今日からタイピング練習を始めてみましょう。
未来の自分のために、今できることを一歩ずつ。
学習まんがを無料で読むならガッコミで!
今知っておきたいニュースに関するお話も読める「ガッコミ」は、Gakkenが運営する無料のまんがポータルサイトです。子どもから大人まで楽しめる作品が満載で、歴史や科学、ゲームを題材にしたまんがが定期的に更新されています。学びながら楽しめる作品がそろっており、家族みんなで楽しむことができます。
心がうごく、世界が広がるまんがサイト ガッコミ
【ガッコミ 3つの特長】
1. 豊富なジャンルのまんがが読める!
歴史や科学の知識を深められる「学研まんが NEW日本の歴史」シリーズや、人気ゲーム「桃太郎電鉄」を題材にした地理・歴史攻略まんがなど、幅広いジャンルを網羅。定番のロングセラー作品も多数掲載されています。
2. 誰でも利用できて無料で楽しめる♪
登録不要で、すべての作品を無料で読むことができます。低年齢層のユーザーにも使いやすいデザインが特徴で、簡単にまんがを探して楽しむことができます。
3. いつでもどこでも読めるオンライン形式◎
スマホやタブレット、PCから簡単にアクセス可能。通勤・通学の合間やリラックスタイムなど、好きな時間にまんがを楽しむことができます ガッコミは、学びとエンターテインメントを両立させた新しい形のまんがポータルサイトです。歴史や科学、ゲームの世界に浸りながら、知識と感動を手に入れましょう。